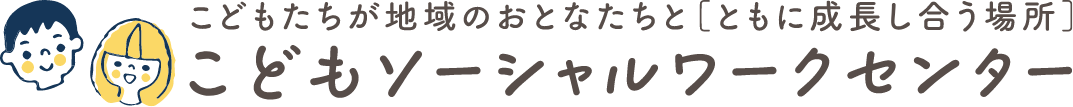チャイルドラインの公開講座に参加しました
NPO法人CASNさんと、滋賀県子ども若者部さんが主催している「こどもたちの“今”を知る公開講座」にネットワーク活動を学ぶために実習生が参加しました。 22日には実習生のたかちゃんが、23日には実習生のたかちゃんとさかじゅんが参加しました。
22日の午前中は、「ときめき自分探しツアー」というテーマで近江富士花緑公園園長の島川武治先生の講演でした。ゲームを通して、参加者同士が仲良くなったあと、後半は、回想から今の自分を見つめてみましょうというワークを行いました。そのワークをする中で、なぜ私がこどもの福祉に関心があるのか、今後どのようなことをしたいと思っているのかが整理できたように思います。
午後からは、「子どもの権利 子どもの話をきくこと」というテーマで、龍谷大学社会学部教授の山田容先生からお話をききました。子どもの権利条約で「子どもの意見の尊重」をうたっているが、こどもは安心して話ができる状況にないと話をすることは難しい。何気ないやりとりの中で大切な思いが浮上し、雑談の延長に吐露、相談がある。だから居場所が必要なのだというところに感銘を受けました。
では、実際にどのようにこどもの声を聴いたら良いのでしょうか?それは次の日の講座のテーマでした。
11月23日には「電話で支える ~こころを繋ぐ~」という講座を受講しました。講師の宮脇宏司先生は公認心理士として長年活動をされている方です。この講座では、聞き手としての技術を教わりました。
宮脇先生の言葉の中で特に印象に残っているのが、「(相談者に対して、)いいことや答えを言おうとしなくていい。そこにいて、話を聴いてくれればそれでいい」という言葉です。相談者が話す”言葉”ばかりを追うのではなく、相談者の”声”の調子を感じ取り、感情の変化に合わせて相づちを打っていくことが大切だと学びました。午後には、そのような聴き方ができるように、受講者同士で実践をしました。この実践では「普段の2倍以上の相づちを打つ」ことを目標に聞き取りを行いました。実践をしてみて、聞き手が「多すぎる」と思うぐらいの相づちを打っても、実は相談者にとっては「ちょうどいい」と思えることが多いことが分かりました。このような聴き方をしていると、はじめは緊張をしていた相談者も、話が終わるころには、明るい表情でどんどんと話すように変化していました。相談者の”声”に耳を傾けることは、相談者自身が持つ力を取り戻させるような効果があると感じました。
雑談の中で、こどもたちの楽しさ、ちょっとした愚痴がいえるような居場所として、センターの活動があるのだろうと思った。